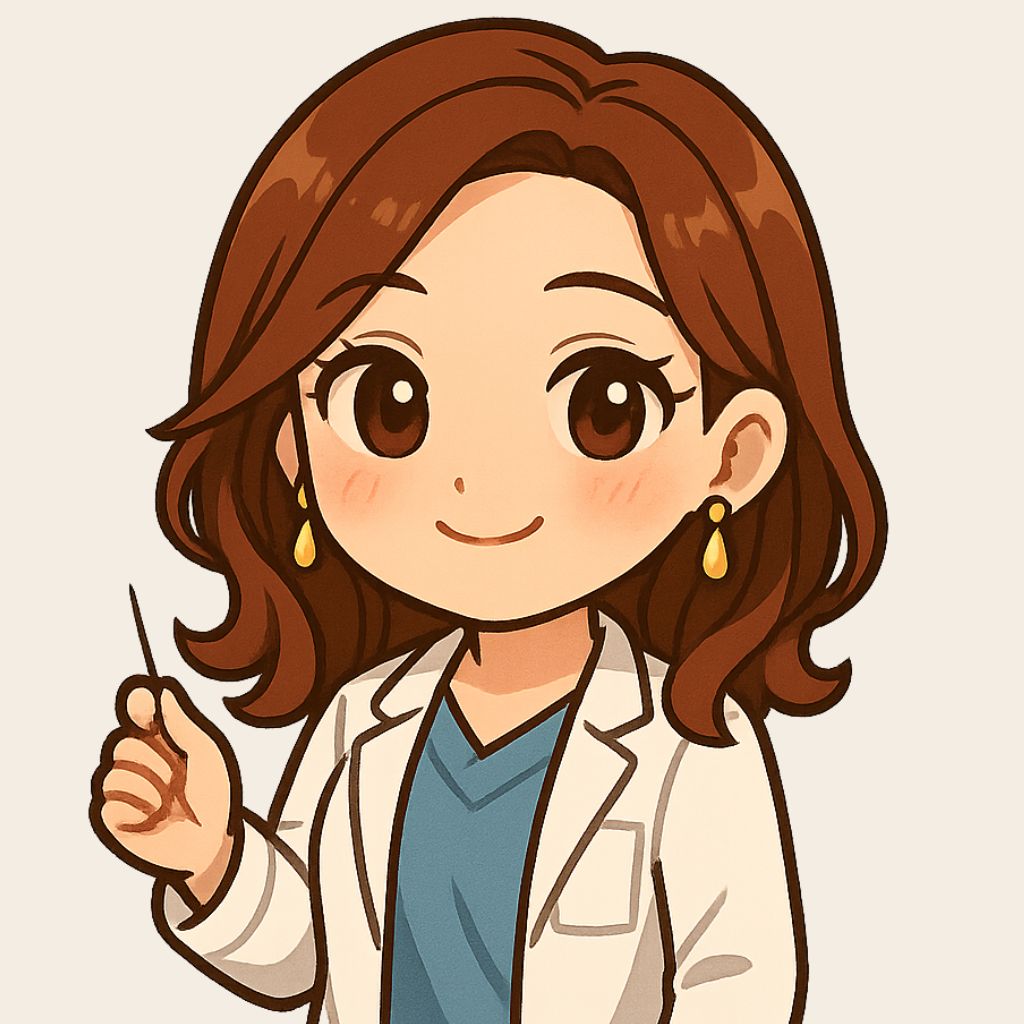鍼灸師は「施術」や「臨床」の勉強はたくさんしますが、
ハラスメントや労務リスクについて学ぶ機会はほとんどありません。
しかし現場では、
上司‐スタッフ間のパワハラ
患者‐施術者間のセクハラ
クレーマー対応(カスハラ)
業務委託と雇用の線引き
など、“グレーゾーンが多い”働き方が一般的です。
トラブルを避けるには技術だけでは足りません。
働く側も守られるためのリテラシーが必要です。
今回、ハリトヒトの「未病リーガル講座(ハラスメント回)」を視聴し、
鍼灸院にこそ必要だと感じたポイントをまとめました。
鍼灸院は一般企業ともクリニックとも違う「特殊環境」
鍼灸院は小規模事業が多く、
実際には“医療機関のようで医療機関ではない環境”です。
そのため、
管理職とスタッフの関係
施術者と患者の関係
シフト管理や拘束時間
労働契約の曖昧さ
など、一般企業とは別のリスクが生まれます。
講座では、この“鍼灸院特有の構造”を踏まえながら、
ハラスメントが生まれやすい背景を丁寧に説明してくれていました。
「何がアウトなのか」を知らないまま働く怖さ
私自身も現場に出て強く感じますが、
そもそも何が違法で、何がハラスメントなのかを学ばずに卒業する人が多い。
これってパワハラ?
患者のこの言動ってセクハラ?
シフトの拘束って合法?
業務委託なのに勤務時間の縛り?
こうした判断軸がないまま働くのは本当に危険です。
講座では、
「まずは定義を知ること」「基準が分かれば対処できる」
という基本をしっかり教えてくれていました。
チームで共有し、院内の“対応ルール”を作る大切さ
最近、年齢の近い院長とチームビルディングを話し合うことが増えました。
そこで感じるのは、
ハラスメント対策は個人の努力では限界があるということ。
院内で起こりうるケースを共有する
対応フローを決める
F&A(対応集)として記録する
こうしてナレッジを積み上げることが、
スタッフの心理的安全性を守るための“仕組み”になります。
ハラスメントが発生した際の“管理者の責任”
鍼灸院でハラスメントが発生した場合、
事業所の管理者(院長・マネージャー等)には必ず対応義務が生じます。
これは“善意の対応”ではなく、
法律で定められた「職場環境配慮義務(安全配慮義務)」に基づくものです。
管理者がハラスメントを放置した場合、
以下の重大なリスクが発生します。
1)職場環境配慮義務違反(債務不履行)になる
労働者には「安全な職場環境で働く権利」があり、
使用者(事業主)には
その環境を維持する義務があります。
ハラスメントを把握しているにもかかわらず
対応しない・調査しない・改善しないという行為は、
=安全配慮義務違反
=債務不履行
と判断される可能性が高くなります。
2)損害賠償請求のリスク
被害者から
- 精神的苦痛に対する慰謝料請求
- 治療費・休業補償の請求
- 使用者責任に基づく損害賠償請求
などを受ける可能性があります。
また、加害者本人も別途、
被害者から損害賠償請求を受けることがあります。
3)人材流出・職場崩壊につながる
ハラスメントを見過ごす職場は、
スタッフ間の信頼が失われ、
心理的安全性がない組織になります。
その結果、
- 離職率の増加
- 定着率の低下
- 生産性の低下
- 採用難
という悪循環を引き起こします。
4)レピュテーションリスク(信用失墜)
小規模な鍼灸院ほど、
口コミや評判による影響が大きくなります。
ハラスメント問題が表に出れば、
- 患者離れ
- 新規の来院数の減少
- SNSでの批判
- スタッフ採用の困難化
など、経営に直接的なダメージとなる
ブランド毀損リスクが発生します。
5)行政からの指導を受ける可能性
労働施策総合推進法に抵触する場合、
行政からの指導・改善命令の対象となる可能性があります。
特に、
- ハラスメント相談窓口がない
- 相談後の調査・対応が行われていない
- 加害行為が継続している
- 是正措置が不十分
といった場合は、行政対応が強化される可能性があります。
管理者が取るべき行動
- 事実確認(ヒアリング・記録)
- 被害者の安全確保
- 加害者への指導・是正措置
- 再発防止策の策定
- 組織内での共有(個人情報に配慮した範囲で)
“何もしない”ことが最悪の選択肢です。
対応の遅れは、
被害者だけでなく事業所自身を危険にさらします。
ハラスメントの放置は、
“ただのトラブル”ではなく
事業所に法的・経営的ダメージを与える重大リスクです。
管理者は、
すぐに行動し、環境を整える義務がある。
これを理解しているかどうかで、
治療院の未来は大きく変わります。
「古い体質の治療院で働いている場合、どうしたらいいのか」
1. 現実として、古い体質の治療院はまだ存在する
昔ながらの“師弟制度”のような雰囲気
「うちはこうだから」とトップダウンで変化を拒む上司
ハラスメント研修や労務知識を“必要ない”と考える経営者
こうした環境は今も珍しくありません。
2. 現場で働く側としてできること
まず「自分の心身を守ること」を最優先にする
その環境で働き続けて、
精神的にも身体的にもストレスが蓄積しているのであれば、
私は 転職を選択肢に入れることを強くおすすめします。
心がすり減ったあと、身体症状が出てしまってからでは
回復に時間とエネルギーが必要になります。
〈健康〉と〈働く場所〉は、取り替え可能なものではありません。
すぐに何らかのアクションを取りたい場合は
行為が度を越えている、明らかに違法性が疑われる場合は
労働基準監督署へ相談する
労働基準監督署とは、会社が労働法令をきちんと守っているかどうかをチェックし、必要があれば会社に指導・改善を働きかける機関です。厚生労働省が管轄しています。
主に、未払い残業代、給与の遅配、最低賃金、時間外労働、休憩時間、有給休暇、労災問題などについて相談できます。
弁護士(労働問題)に相談する
という“民事的なルート”を使うのが最も確実です。
3. 問題のある職場そのものを変えるには
正直なところ、
その職場がすぐに変わる可能性は低いのが現実です。
しかし、“個人”ではなく“外部”から働きかけることで、
中長期的には環境を変えることができます。
中長期的なアプローチ
業界団体に対して
「ハラスメント定義・注意喚起・講習受講の促進」を求める
【2025年対応版】病院・クリニック向けハラスメント防止研修|パワハラ・カスハラ対策を社労士講師が支援 | リーサス社労士事務所
医療機関のカスタマーハラスメント対策を社労士が解説!経営者が知っておくべき職員を守る方法【セミナーレポート】
同業者が集まる労働組合的なグループをつくり、
事例共有や意見表明を継続する
SNS・専門メディアで啓発していく
(個人攻撃ではなく、構造的な問題として論じる)
これらの“外圧”が積み重なることで、
「ハラスメント研修を受けるのが当たり前」という
スタンダードが後から形成されていきます。
個人と業界を守るために
自分の身を守る術を知ること
環境を選ぶ権利があること
外部機関に相談できること
業界全体に声を上げてもいいこと
これらを知るだけでも、
今いる環境が“唯一の選択肢ではない”と思えるはずです。
鍼灸師が安心して働ける現場づくりは、
一人ひとりのリテラシーと小さな行動から始まります。
次回以降の回も、鍼灸師は見て損しない
未病リーガル講座は随時開催で、
毎回テーマが違い、どれも現場の鍼灸師に直結する内容です。
次回のテーマもきっと、
・働き方
・労務
・法律
・チーム運営
など、今の時代に必要な内容が扱われると思います。
「業務委託」「偽装請負」についても今後お話ししていただけるそうです。こちらは個人的にかなり視聴したいテーマです。
鍼灸院で働く人、独立する人、スタッフを抱える人、
すべての鍼灸師におすすめしたい講座です。
施術技術は大切です。
しかし、自分を守る力(法務・労務リテラシー)も同じくらい大切です。
ハラスメントやトラブルへの耐性は、
“知識”があるだけで大きく変わります。
業界を良くするためにも、まずは
「知ること」から始めませんか?
次回の未病リーガル講座、
ぜひ一緒に視聴しましょう。